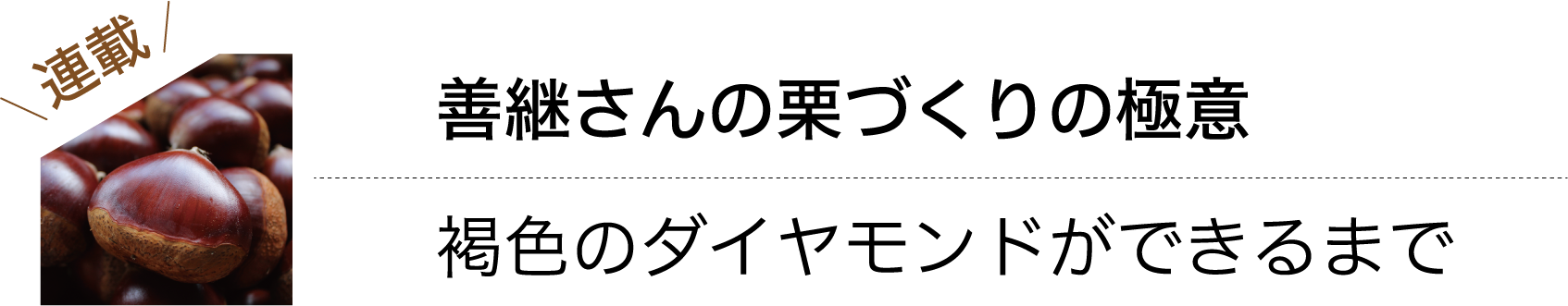栗の剪定が味を決める
「美味しい栗づくりは、剪定で決まる」と善継さんは言います。剪定とは、木の成長を整え、実付きや品質を左右する大切な作業です。栗の木が休眠に入る 12 月から 3 月の間に、余計な枝を落とし、日当たりや風通しを良くすることで、翌年の実の成長を促します。

栗は果実が成った後に摘果するのではなく、冬の剪定で枝の調整を行うことで、実の大きさや収穫量をコントロールします。
「剪定の目的は、どの枝にも太陽の光が満遍なく当たるようにすること。太陽は移動しますから、いろんなところから枝に日が当たる、それを想定しながら剪定します。栗畑をくまなく巡り、一本一本の木を眺め、日光を遮ったり風通しを悪くしそうな枝、他の枝とぶつかりそうな枝を確認して、大きいものから順に切っていきます」。

剪定の技と工夫
剪定に使う道具は、枝の太さやついている角度、高さによって使い分けます。チェーンソー、高枝ノコギリ、高枝バサミ、手元用ノコギリやハサミ。それぞれの特性を活かしながら、木の形を整えていきます。
「大きな枝はチェーンソーで、高い場所の枝は梯子を使ってガッツリと切り落とします。隙間にある枝はノコギリで、細い枝はハサミで丁寧に切り落とします。道具の手入れは大切です。いつどんな枝でも切れるようによく手入れしておきます」
剪定は、花の近くから切っていきます。「よく見ると枝にタコの吸盤のようなくぼみがあります。それが前年に実がついたところです。同じ枝から芽が出て実がつきます。深く切りすぎると実がならないので前年に伸びた枝を観察しながら一番充実したところを切る。適切な長さで剪定すれば、一つの枝に3つか4つほどの実がつきます」。

剪定の仕方次第で、栗の実は大きくも小さくもなります。枝の数を減らせば、より大きな栗が育ちますが、収量は減ります。
「4Lサイズという大きな実を育てると全体の収穫量は下がり、2L3Lサイズだと収量は増えます。また、それより小さいサイズになるとまた収量が減ります。大きな栗は風にさらされるとカサカサになったりするので、生栗は店頭販売にはあまり向かず、主に加工用として利用されます。ですから、実が崩れにくくて火が通りづらい4Lよりも、2L3Lがいちばん喜ばれます。こういうことが、80 になってからやっとわかってきました(笑)」。 市場のニーズを考慮しながら、最適なバランスを見極めることも、栗づくりの奥深さのひとつです。
パラソルカットで陽を届ける
善継さんが取り入れている剪定技法のひとつが「パラソルカット」。これは、木の中心部の枝を高く伸ばし、下の枝が横に広がるように整える方法です 。木全体がまるで傘を開いたような形になり、どの枝にもまんべんなく日が当たります。

「私の栗園では木を3m50cmぐらいの高さに揃えていますが、下の枝と上の枝を 1m50cm 以上空けることで、どの枝にも日が当たるようにします。飛行機の邪魔にならんようになら、どこまで伸ばしても大丈夫と言ってますが(笑)ぐんぐん伸ばして、途中の枝は思い切って落とすと、上と下の両方の枝が陽の光をたっぷり浴びて実がたわわになるというわけです。厚かましい方法ですね(笑)」
剪定した枝は、チップや薪にして再利用します。山内さんの孫が枝拾いを手伝うこともあり、家族総出で栗づくりに励んでいます。

「今年はどれだけたくさんの実がつくかな?」
そのことを何よりも楽しみにしながら、善継さんはハサミを手に、迷いなく枝を落としていきます。その姿には、83 歳になった今も変わらない、栗づくりへの情熱が宿っていました。